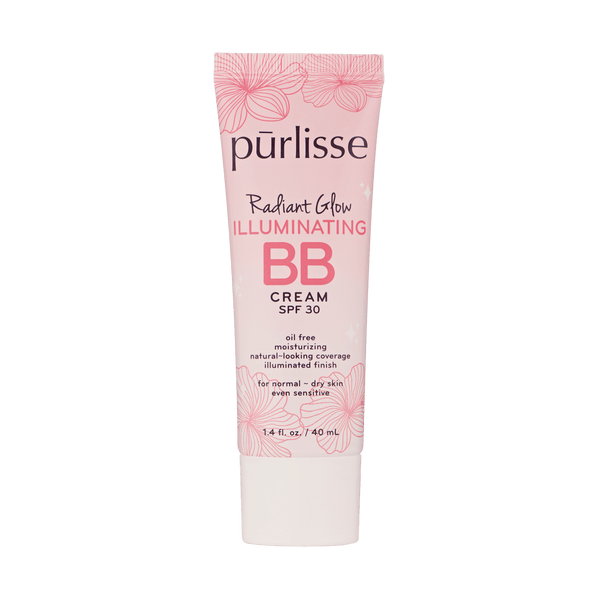Note Cosmétique Algérie - Voici les 3 teintes disponibles sur notre BB crème #notecosmetics #notecosmeticsalgerie | Facebook

Note Cosmétique - BB Creme, soin pour la peau et pour le visage hydratant, Fond de Teint Couvrant Imperfections, Anti Cerne, Palette Maquillage Femme : Amazon.fr: Beauté et Parfum